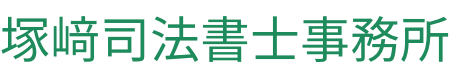任意後見とは?制度について解説
高齢化が進む現代社会では、将来の判断力低下や認知症への備えが重要な課題です。
家族や自分の将来に不安を感じる方も多く、元気なうちにできる対策を知っておくことが求められます。
そこで注目されているのが、事前に備えるための法的制度です。
本記事では、そのひとつである任意後見について解説します。
任意後見とは?
任意後見とは、将来判断能力が不十分になったときに備えて、本人が元気なうちに自ら後見人を選任しておく制度です。
公正証書で「任意後見契約」を結び、実際に判断能力が低下したときに、契約に基づいて支援を行います。
この制度は、介護、生活支援などを本人の希望に沿って柔軟に対応できる点が大きな魅力です。
任意後見の利用の流れ
任意後見は、以下の流れで行うことが一般的です。
- 契約の準備と公証役場での契約
- 任意後見監督人の選任
- 任意後見人の業務の開始
ひとつずつみていきます。
契約の準備と公証役場での契約
まずは信頼できるひとと任意後見契約を締結し取り決めを行います。
その後、公証人の立ち会いのもとで公正証書にします。
これにより「将来の後見人」が決まります。
任意後見監督人の選任
本人の判断能力が低下し、任意後見契約の効力が発生するタイミングで、任意後見をきちんと行っているか監視するため選任を家庭裁判所に申し立てます。
選任が認められると、契約内容に基づいた後見が開始されます。
任意後見人業務の開始
任意後見人は定期的な任意後見監督人への報告書・財産目録・資料等の提出などの業務を担います。
万が一、業務を怠った場合や、職務を怠り不正な行為を行った場合は、解任される可能性があります。
また、任意後見監督人の選任後に一方的に契約を解除することも、正当な理由がない限り認められません。
まとめ
任意後見制度は、将来の不安に備え、信頼できるひとに自ら支援を託すことができる柔軟で安心感のある仕組みです。
判断能力があるうちに契約する必要があるため、早めに制度を理解し、司法書士などの専門家に相談しながら準備することが大切です。