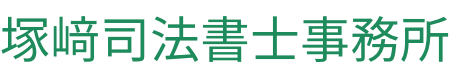公正証書遺言の作成方法とは?手続きと必要書類を解説
相続トラブルを防ぐために、もっとも確実とされるのが「公正証書遺言」です。
法律上の要件を満たし、公証人が関与するため、遺言の有効性をめぐる争いが起きづらくなります。
本記事では、初心者にもわかりやすく「公正証書遺言の作成方法」を解説します。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、遺言者が口述した内容を、公証人が法的に正しい形式で書き起こし、署名・押印を行った遺言書です。
証人2名の立ち会いが必要で、内容に不備があることはまずありません。
さらに、作成された原本は公証役場に保管されるため、改ざんや紛失の心配もなく、家庭裁判所での検認も不要というメリットがあります。
公証役場で遺言書を作成する前の準備
まず、相続させる財産・相続人・付言事項などの遺言に記載したい内容を整理します。
必要であれば、司法書士など専門家のアドバイスを受けるのも有効です。
内容が固まったら、公証役場に連絡し、遺言作成の予約を取ります。
このとき、公証人に事前に草案や資料を送付しておくとスムーズです。
作成に必要な主な書類は次の通りです。
- 遺言者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 財産関係の資料(登記簿謄本、通帳コピー、不動産評価証明書など)
- 相続人の戸籍謄本、住民票
当日は公証役場、または公証役場へ出向くことができないひとは自宅・病院などで、公証人が遺言内容を読み上げた後、遺言者と証人が署名・押印します。
公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料が主で、財産額に応じて変動します。
たとえば、1,000万円の財産の場合、手数料は約23,000円程度が目安です。
証人手配料や出張費が別途必要になることもありますが、安全性を重視するなら十分にあるといえます。
まとめ
公正証書遺言は、形式不備や無効のリスクが最も低く、相続トラブルを防ぐうえで非常に有効な方法です。
作成には公証役場との調整や証人の手配、書類準備が必要ですが、その分、法的な信頼性が高く、安心して家族に財産を遺すことができます。
手続きに不安のある方は、早めに司法書士などの専門家への相談を検討してみてください。