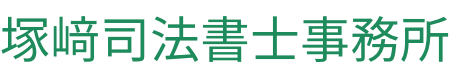法定後見とは?制度の目的や手続きの流れを解説
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分になった人の財産や権利を守るための制度が「成年後見制度」です。
その中でも「法定後見」は、家庭裁判所が後見人を選任して支援を行う仕組みです。
本記事では、法定後見の概要と類型、利用の流れを解説します。
法定後見とは?
法定後見とは、本人の判断能力がすでに低下している場合に、家庭裁判所が本人に代わって適切な後見人を選び、法律行為や財産管理をサポートする制度です。
これは、将来に備えて契約で後見人を指定しておく任意後見とは異なり、本人の意思によらず家庭裁判所が関与して開始される点が特徴です。
3つの類型|後見・保佐・補助
法定後見制度には、判断能力の程度に応じて3つの類型があります。
- 後見人
- 補助人
- 保佐人
ひとつずつみていきます。
後見人
後見人は、判断能力をほとんど失ったひとに代わり、財産の管理や契約の締結と取消し、年金の受取、施設入所の手続きなど幅広く行います。
本人に重大な不利益が及ばないよう、すべての法律行為を包括的にサポートできるのが特徴です。
特に、高齢者や認知症のひとの生活や財産保護に大きな役割を果たします。
保佐人
保佐人は、判断能力が著しく不十分なひとを支援するために選任されます。
借金、遺産分割、保証契約などの重要な財産行為には、保佐人の同意が必要です。
本人の意思を尊重しながら、法的リスクの高い行動を防ぐ役割を担います。
補助人
補助人は、判断能力が一部分のみ不十分なひとに対して、範囲を限定して支援を行います。
本人の同意を前提に、特定の法律行為について同意権や代理権が付与されます。
たとえば、銀行の手続きや施設入所の契約など、日常生活の中で支援が必要な場面に応じて柔軟に対応します。
まとめ
法定後見とは、判断能力が不十分になった人の生活と権利を守るために、家庭裁判所が後見人を選び支援を行う制度です。
後見・保佐・補助の3つの類型があり、本人の状態に合わせて適切な保護が図られます。
身近な人に判断能力の不安がある場合は、早めに制度の利用を検討し、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。