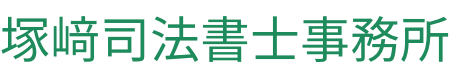相続手続きの流れとは?必要な手順と期限を解説
相続が発生すると、さまざまな手続きを進める必要性がでてきます。
中には期限付きのものも多く、知らずに放置すると不利益を受ける可能性があります。
本記事では、相続手続きの流れや手順、それぞれの期限について解説します。
死亡直後から3ヶ月以内に行う手続き
3ヶ月以内に判断すべきことは以下のとおりです。
- 遺言書の有無を確認
- 相続財産と法定相続人を把握
- 相続人を確定する
相続は、被相続人(亡くなった方)の死亡と同時にスタートします。
最初に取り組むべきは、自筆か公正証書遺言書なのかを含めた遺言書の有無と、戸籍謄本などの収集を通じた相続人の調査です。
また、相続放棄や限定承認を行うための、相続財産の調査も必須です。
これらの手続きは期限を過ぎると、期間の伸長の手続きを踏まなければ、単純承認とみなされるため注意が必要です。
準確定申告など4ヶ月以内に必要な対応
次に対応すべきは、被相続人の所得に関する申告です。
被相続院の所得税を計算するための、準確定申告という手続きが必要となります。
準確定申告は、原則的に相続人全員の連名で税務署へ申告する必要があります。
被相続人の源泉徴収票や医療費控除の明細などの書類が必要になるため、事前の準備が大切です。
遺産分割協議と名義変更の流れ
相続人が確定し、財産の内容が明らかになったら、遺産を誰がどのように受け取るかを相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行います。
協議内容は「遺産分割協議書」として文書化し、全員の署名・押印を行うことで正式な合意となります。
この書類をもとに、不動産は法務局で相続登記を、預貯金は各金融機関で名義変更や払い戻しの手続きを進めます。
不動産の相続登記は2024年から義務化されており、3年以内に手続きをしなければ過料が科される可能性があるため注意が必要です。
相続税の申告と納税など10か月以内に必要な対応
相続税の基礎控除額を超えた場合、相続開始の翌日から10か月以内に、申告と納付を行う必要があります。
遺産分割が未了でも期限までに申告しなければ、延滞税や加算税が課される可能性があります。
まとめ
相続手続きは、死亡届の提出から始まり、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、名義変更、相続税申告まで多くの工程を経て完了します。
それぞれに期限があり、放置すると不利益があることもあります。
特に、相続放棄や相続登記は法律上の期限があるため、早めの対応が不可欠です。
困ったときは司法書士などの専門家への相談を検討してみてください。