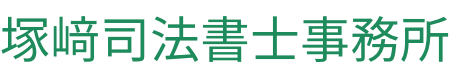遺言書の種類とは?3つの方式と選び方をわかりやすく解説
相続トラブルを避けたいと考えるなら、遺言書の作成は非常に有効です。
遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ作成方法や効力、メリット・デメリットが異なります。
本記事では、代表的な3つの遺言書の種類について解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印することで作成する遺言書です。
財産目録はパソコンで作成が可能なため、手間を削減できます。
公証人などに頼らず自分ひとりで作成できるため、もっとも手軽で費用もかかりません。
ただし、形式不備や内容のあいまいさから、無効と判断されるケースが少なくありません。
また、家庭裁判所での「検認」手続きが必要で、開封前に申立てが必要です。
2020年から法務局での保管制度も始まり、これを利用すれば検認が不要となるため、安全性を高めたい場合は積極的に活用すべきです。
自筆証書遺言を法務局で保管する場合、手数料が3,900円かかります。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人に内容を伝え、法的に正しい形式で作成・保管してもらう方式です。
証人2名の立ち会いが必要ですが、遺言の形式ミスや内容の不備がなく、もっとも安全性・信頼性が高い遺言書とされています。
さらに、家庭裁判所の検認も不要なため、遺言執行がスムーズに進みます。
一方で、公証人手数料や証人手配などに一定の費用と手間がかかるため、費用面などが気になるひとは事前に金額を確認しておくと安心です。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、本人が遺言の内容を記した文書に署名・押印し、遺言を封筒に入れて封印したうえで、証人2人と一緒に公証役場で作成日と存在を証明してもらう方式です。
特徴は、内容を秘密にできることにあります。
たとえ証人や公証人でも、遺言の中身までは把握できません。
しかし、内容のチェックがされないため、形式の不備や封を開けると無効になるリスクがあり、かつ検認も必要です。
遺言書の選び方
どの遺言書が適しているかは、目的や家族構成、費用、秘密性の有無などによって変わります。
手軽さを重視するなら自筆証書遺言が選ばれますが、安全性や法的トラブルの回避を重視するなら公正証書遺言が推奨されます。
内容を他人に知られたくない場合には、秘密証書遺言も選択肢になりますが、形式ミスのリスクを考えると慎重な判断が必要です。
まとめ
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれメリットとリスクが存在します。
費用や手軽さを重視するか、安全性と確実性を重視するかで最適な選択肢は変わります。
もし迷う場合は、司法書士などの専門家への相談を検討してみてください。